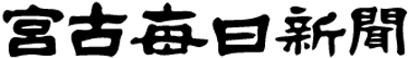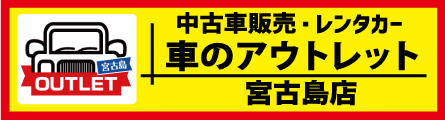高齢者の大腿部骨折多い/宮古、全国の2倍
琉大が調査報告 「元気さが災い?」
高齢者に多い大腿骨骨折の宮古での発生率が際立って高いことが、琉球大学医学部高次機能医科学講座の実態調査で分かった。宮古の発生率は、全国平均の約2倍、北海道浦河町の6倍だった。宮古がなぜ高いのか、明確な理由はつかめていない。同講座の大湾一郎琉大准教授が16日、調査に協力した医師らを対象に報告した。
骨折予防策立案等を目的とする同調査は、全国6地区で実施。宮古では、宮古病院など9医療施設が協力した。調査の期間は、2010年の1年間。大腿骨骨折や脊椎錐体骨折など、4種類の高齢者骨折について発生数や発生率、患者の骨折既往歴などを調べた。
4種類のうち、大腿骨骨折は歩行不能や寝たきりになるケースが多いため、予防が重要視されているという。
宮古での大腿骨骨折の患者は、134人。人口1000人当たりの発生率は6と、全国6地区中最も高かった。男性が26人、女性が108人と男性1人に女性4人の割合だった。
骨折した高齢者のほとんどは骨粗鬆症の人だが、109人が治療をしていなかった。大湾准教授は、全員が治療をしていたとすれば「骨折は半分ぐらい防げた」と推測した。
受診者の受傷前の元気度を示すバーテルインデックスは81・7と沖縄県平均の76・8より高かった。宮古の人は歩いている時や洗濯物を干しに行く際などに転んで骨折するケースが多いことから、大湾准教授は「宮古の場合は、元気さが逆に災いしているのでは」との見方も示した。
4種類の高齢者骨折のうち、脊椎錐体が227人と最も多かった。
予防対策としては①転倒・骨折に対する啓蒙活動②骨粗鬆症治療の普及③活動性の高い高齢者に対するレク活動-などを示した。