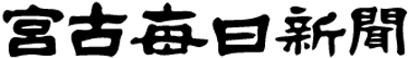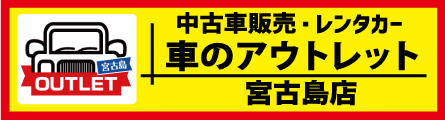キビ黒穂病広がる/宮古全域
病害虫対策協 「被害圃場で採苗やめて」
収量の減少を招くサトウキビの黒穂病が宮古全域で確認されている。発生圃場率(6月中旬現在)は31・3%と、前年同時期の16%のほぼ2倍となっている。研究員らは栽培品種が偏っていることや、防除意識が浸透していないことを踏まえて被害のまん延に警戒を強めている。農家に対しては黒穂病にかかったキビは直ちに引き抜くよう助言。被害圃場のキビを苗として使用することも「絶対にやめてほしい」と呼び掛けている。
黒穂病は、キビの先端から黒いカビの胞子が付いた穂が出てくるのが特徴。胞子は風雨で飛び散って周囲に伝染するとされる。
黒穂病が出たキビは、その時点で生育が止まる。枯死することはないが、収量の減少は免れない。
宮古地区病害虫防除対策協議会は6月に調査を実施した。一本でもかかった茎があれば「1」とカウントする発生圃場率と、100本中の罹病茎を数える発病株率を調べた。
この結果、宮古地区の株出し栽培における発生圃場率は31・3%。春植えは調査外、夏植え圃場ではほとんど見られなかった。
地区別では、伊良部が最も高い66・7%で、以下▽下地53・3%▽平良%▽城辺6・7%-だった。
発生株率は全体で1・1%にとどまっているが、被害地域に偏りがあり、一部の圃場では23・5%という高い数字が出ている。
県農業研究センター宮古島支所の研究員は「被害は確実に広がっている」と警鐘を鳴らし「黒穂病が発生した圃場からは苗を採らないでほしい」と次期作に伝染させないよう注意を促している。
黒穂病にかかったキビはカビの胞子が飛び散らないようにビニールをかぶせて抜き取ることも被害の拡散防止に有効だとした。
また、宮古地区における品種の偏り(全体の71%が農林27号)にも触れ、「決して農林27号が悪いというわけではないが、品種を変えることで更新が進んで発生を抑えられる」とし、多様な品種構成を効果的な防除法の一つに挙げた。